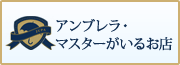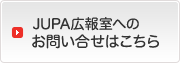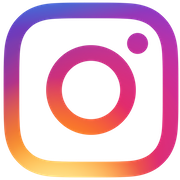忘れ傘
2004.01.01
 半村良
半村良
(集英社・1985年8月刊)
第72回直木賞を受賞し、昨年68歳で亡くなった半村良が、1985年に発表した短編集。表題の作品は男女の関係を大人の視点で紡いできた著者ならではの、少し辛口な恋愛ロマンだ。発表の翌年に同タイトルでテレビドラマ化もされているので、あるいはご記憶の方もいるかも知れない。ちなみに直木賞の受賞作も「雨やどり」という雨に関したタイトルの作品だった。
雨の日に始まった主人公である実業家の男性と行きつけのクラブでホステスの恋。その場面を何気なく演出したのが店に置かれた忘れ物の傘だった。男性は何気なく忘れ傘の存在について考えるが、その時はこの忘れ傘と自分の恋が重なってくるとは思いもよらなかった。
傘は個人が持つものではあるが、貸したりもらったりすることで、他の人の手に渡ることも少なくない。人から人へと渡り行くなかで、その傘にちなんだ情景も変わっていく。たまたま店に忘れられていった傘も、元々は持ち主から大事に扱われていた傘だったのかもしれない。
そんな忘れ傘を、著者は次のように表わしている。「誰がさしてもよく、返す必要もない。それでいて店が用意しているサービス用のビニール傘よりよほど品物がいい」。
文中でこの忘れ傘に喩えられているのがホステスの女性だ。人生を素直に歩むことを嫌い、何か楽しいことが起きるのを漠然と待ち続けてきた。そんな時に主人公の男性と出会い、夢のような日々が始まる。主人公も彼女の飾り気のない天真爛漫な人柄に惹かれ、次第に結婚も考えるようになる。しかし彼女の夢が覚めた時、主人公はようやく自分もその夢の世界に引き込まれていたことに気づく。そして自分が元々持ち主がいた忘れ傘を差していたのだということにも。主人公は彼女を忘れ傘に置き換えることで、彼女の存在を理解し、そしてそれを持つ人と自分の気持ちを重ね合わせた。
一本の傘を通して見る人の気持ちや存在。何も語らずに人から人の手に渡る傘だが、だからこそ自分が手にした傘がどのようにして自分のところにたどり着いたのか想像してみるのは面白い。作り手の思い、売る人の気持ち、そして誰を通して自分のもとに傘が届いたのか。それぞれの人が実際に同じハンドルを持ち、留め金を外して傘を開いてきたのだ。その時々の思いを推し量ることで、傘に対する愛着もより強いものとなるのではないだろうか。
 半村良
半村良(集英社・1985年8月刊)
第72回直木賞を受賞し、昨年68歳で亡くなった半村良が、1985年に発表した短編集。表題の作品は男女の関係を大人の視点で紡いできた著者ならではの、少し辛口な恋愛ロマンだ。発表の翌年に同タイトルでテレビドラマ化もされているので、あるいはご記憶の方もいるかも知れない。ちなみに直木賞の受賞作も「雨やどり」という雨に関したタイトルの作品だった。
雨の日に始まった主人公である実業家の男性と行きつけのクラブでホステスの恋。その場面を何気なく演出したのが店に置かれた忘れ物の傘だった。男性は何気なく忘れ傘の存在について考えるが、その時はこの忘れ傘と自分の恋が重なってくるとは思いもよらなかった。
傘は個人が持つものではあるが、貸したりもらったりすることで、他の人の手に渡ることも少なくない。人から人へと渡り行くなかで、その傘にちなんだ情景も変わっていく。たまたま店に忘れられていった傘も、元々は持ち主から大事に扱われていた傘だったのかもしれない。
そんな忘れ傘を、著者は次のように表わしている。「誰がさしてもよく、返す必要もない。それでいて店が用意しているサービス用のビニール傘よりよほど品物がいい」。
文中でこの忘れ傘に喩えられているのがホステスの女性だ。人生を素直に歩むことを嫌い、何か楽しいことが起きるのを漠然と待ち続けてきた。そんな時に主人公の男性と出会い、夢のような日々が始まる。主人公も彼女の飾り気のない天真爛漫な人柄に惹かれ、次第に結婚も考えるようになる。しかし彼女の夢が覚めた時、主人公はようやく自分もその夢の世界に引き込まれていたことに気づく。そして自分が元々持ち主がいた忘れ傘を差していたのだということにも。主人公は彼女を忘れ傘に置き換えることで、彼女の存在を理解し、そしてそれを持つ人と自分の気持ちを重ね合わせた。
一本の傘を通して見る人の気持ちや存在。何も語らずに人から人の手に渡る傘だが、だからこそ自分が手にした傘がどのようにして自分のところにたどり着いたのか想像してみるのは面白い。作り手の思い、売る人の気持ち、そして誰を通して自分のもとに傘が届いたのか。それぞれの人が実際に同じハンドルを持ち、留め金を外して傘を開いてきたのだ。その時々の思いを推し量ることで、傘に対する愛着もより強いものとなるのではないだろうか。